
皆さんこんにちは!ロマです!
こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?
今日は『誤嚥性肺炎』についてです!
とても気になりますね!考えるいい機会ですね!
では皆さんで一緒に勉強しましょう!
① 誤嚥性肺炎とは

誤嚥性肺炎とは、食べ物、飲み物、唾液、胃液などが誤って気管や肺に入り、肺に細菌感染を引き起こすことによって発生する肺炎の一種です。特に高齢者や嚥下機能が低下した人に多く見られます。誤嚥性肺炎は、一般的な肺炎と異なり、口腔内や咽頭の細菌が主な原因となります。
【症状】
誤嚥性肺炎の主な症状には以下が含まれます:
発熱:細菌感染による炎症反応で体温が上昇します。
咳:異物を排出しようとする反射的な反応です。
痰:黄色や緑色の痰が出ることがあります。
呼吸困難:肺炎による肺機能の低下で呼吸が困難になることがあります。
食欲不振や倦怠感:全身の炎症反応により食欲が低下し、全身のだるさを感じることがあります。
② 誤嚥性肺炎の原因とは

誤嚥性肺炎の原因は主に以下の要因に分けられます。
嚥下機能の低下
嚥下機能が低下することで、食べ物や飲み物が誤って気管に入るリスクが高まります。例えば、加齢に伴い嚥下筋が弱くなり、正常な飲み込みができなくなることがあります。
口腔内の衛生状態の悪化
口腔内の衛生状態が悪いと、細菌が増殖しやすくなります。特に高齢者は唾液の分泌が減少し、口腔内が乾燥しやすいため、細菌が増殖しやすい環境が整います。入れ歯を適切に清掃しないことも、細菌の繁殖を助長します。
食事中の体位の不適切さ
食事中に体位が不適切であると、誤嚥のリスクが高まります。例えば、ベッドに横たわった状態で食事をすると、食べ物が食道に入りにくく、誤って気管に入る可能性が高くなります。
嚥下反射の低下
神経疾患や認知症などにより、嚥下反射が低下することがあります。これは飲み込みの動作が遅れる原因となり、誤嚥のリスクを増加させます。例えば、パーキンソン病や脳卒中後の後遺症などがこれに該当します。
口腔内の乾燥
唾液の分泌が減少することで口腔内が乾燥し、細菌が増殖しやすくなります。特に夜間は唾液の分泌が少なくなり、口腔内が乾燥しやすくなるため、夜間の誤嚥リスクが高まります。
③ 特養で出来る誤嚥性肺炎の対策とは

特別養護老人ホーム(特養)では、誤嚥性肺炎の予防に向けた様々な対策が行われています。
口腔ケアの徹底
口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防に非常に重要です。以下のような具体的な口腔ケアが推奨されます:
毎食後の歯磨き:口腔内の食べ物の残りかすを除去し、細菌の増殖を防ぎます。
入れ歯の清掃:入れ歯は毎日清掃し、専用の洗浄剤を使用することで細菌の繁殖を防ぎます。
歯科医師や歯科衛生士による定期的な口腔ケア:専門家による口腔ケアで、細菌の除去や口腔内の健康状態の維持が図られます。
嚥下機能の評価とリハビリ
嚥下機能が低下している利用者には、嚥下機能の評価を行い、リハビリを通じて機能の改善を図ります。
嚥下機能の評価:嚥下内視鏡検査やビデオフルオロスコピーなどの検査を通じて、嚥下機能の状態を正確に把握します。
嚥下リハビリ:嚥下機能を向上させるためのリハビリを実施します。例えば、発声練習や嚥下体操、嚥下訓練を行います。
適切な食事形態の提供
利用者の嚥下機能に応じた食事形態を提供することが重要です。
ペースト状やとろみをつけた食事:嚥下が難しい利用者には、固形物を避け、ペースト状やとろみをつけた食事を提供します。
食事中の体位調整:利用者が食事中に直立した姿勢を保てるよう支援し、誤嚥のリスクを低減します。
体位の調整
食事や水分摂取時には、利用者の体位を適切に調整します。
上半身を起こす:寝たきりの利用者には、ベッドを30度以上傾けて上半身を立てるようにします。
食事中のサポート:介護スタッフが利用者の体位をサポートし、適切な姿勢を保てるようにします。
スタッフの教育
介護スタッフが誤嚥性肺炎のリスクと予防方法を理解し、適切な対応ができるように教育を行います。
嚥下機能の評価方法:スタッフが嚥下機能の評価方法を学び、適切な対応ができるようにします。
口腔ケアの重要性:口腔ケアの重要性を理解し、日常的に実践できるようにします。
適切な食事介助:食事介助の方法を学び、利用者に適切な食事形態を提供できるようにします。
④ 誤嚥性肺炎になった時の対応

誤嚥性肺炎が疑われる場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。
早期の医療機関受診
誤嚥性肺炎が疑われる場合、早期に医療機関を受診することが重要です。
症状の確認:発熱、咳、呼吸困難などの症状が見られた場合には、直ちに医師の診察を受けるようにします。
救急対応:症状が重篤な場合や呼吸困難がある場合には、救急車を呼ぶなど迅速な対応が必要です。
抗生物質の投与
医師の指示に従う:医師の指示に従い、適切な抗生物質を使用します。
服薬管理:介護スタッフが服薬管理を行い、利用者が規則的に薬を服用できるようにします。
口腔ケアの強化
治療中も口腔ケアを徹底することが重要です。
歯磨きの頻度を増やす:通常よりも頻繁に歯磨きを行い、口腔内の細菌を減少させます。
うがいの励行:口腔内の清潔を保つために、うがいを頻繁に行います。
嚥下機能の再評価とリハビリ
誤嚥性肺炎を発症した後は、再発防止のために嚥下機能の再評価を行います。
嚥下機能の再評価:医師や言語聴覚士(ST)による嚥下機能の再評価を行い、現在の嚥下能力を正確に把握します。嚥下内視鏡検査やビデオフルオロスコピーを再度実施することがあります。
嚥下リハビリの継続:嚥下機能の向上を図るために、個別に嚥下リハビリを継続します。具体的には、嚥下体操や発声練習を日常的に取り入れます。
食事形態の見直し:嚥下機能に合わせて食事形態を見直し、再度ペースト状やとろみをつけた食事を提供するなどの対応を行います。
栄養管理と水分補給
誤嚥性肺炎の治療中も、適切な栄養管理と水分補給が重要です。
栄養バランスの考慮:必要な栄養素をバランス良く摂取できるよう、医師や管理栄養士と相談して食事メニューを調整します。
水分補給の工夫:とろみをつけた飲み物やゼリー状の水分補給剤を使用して、誤嚥のリスクを減らしながら十分な水分を摂取できるようにします。
家族との連携
利用者の家族との連携を密にし、誤嚥性肺炎の予防と治療に関する情報を共有します。
病状の説明:誤嚥性肺炎の症状や治療方針について、家族に詳しく説明します。
ケアの協力依頼:家庭での口腔ケアや嚥下リハビリについて協力を依頼し、一貫したケアが行えるようにします。
⑤ まとめ

誤嚥性肺炎は高齢者や嚥下機能が低下した人に多く見られる重大な健康問題です。特養では、口腔ケアの徹底、嚥下機能の評価とリハビリ、適切な食事形態の提供、体位の調整、スタッフの教育など、多岐にわたる予防対策が求められます。また、誤嚥性肺炎が発生した場合には、早期の医療機関受診、抗生物質の投与、口腔ケアの強化、嚥下機能の再評価とリハビリ、栄養管理と水分補給などの適切な対応が必要です。
予防の重要性
誤嚥性肺炎は予防が最も重要です。日常的な口腔ケアや嚥下リハビリを徹底し、誤嚥のリスクを最小限に抑えることが重要です。介護スタッフと家族が一丸となって、利用者の健康を守るための取り組みを継続することが求められます。
再発防止策
一度誤嚥性肺炎を発症した利用者には、再発防止策を徹底することが重要です。定期的な嚥下機能のチェックと必要に応じたリハビリの実施、適切な食事形態の維持、継続的な口腔ケアなどを行うことで、再発のリスクを低減させます。
まとめのポイント
誤嚥性肺炎の予防と対応には、利用者一人ひとりの状態に合わせた個別対応が必要です。特養では、専門的な知識とスキルを持つ介護スタッフが、利用者の健康を守るために日々努力を続けています。利用者の生活の質を向上させるためにも、誤嚥性肺炎の予防と早期対応に力を入れることが重要です。
以上が「特養における誤嚥性肺炎」の詳細なブログ記事です。利用者の健康を守るために、誤嚥性肺炎の予防と対応に関する知識を深め、日常のケアに役立てていただければ幸いです。







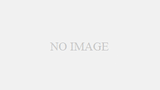
コメント