
皆さんこんにちは!ロマです!
こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?
今日は『労災』についてです!
とても気になりますね!考えるいい機会ですね!
では皆さんで一緒に勉強しましょう!
- 1. 介護職の労災リスクとは?腰痛や感染症は労災になるのか
- 2. 社会福祉施設における労災発生状況
- 3. 介護現場での腰痛やケガは労災になる?
- 4. 新型コロナウイルス感染は労災になる?
- 5. 介護現場での労災事例
- 6. 労災認定後に受けられる給付金とは?
- 7. 労災の申請手続き:どうすればいい?
- 8. まとめ:介護職員が労災に備えるために
1. 介護職の労災リスクとは?腰痛や感染症は労災になるのか
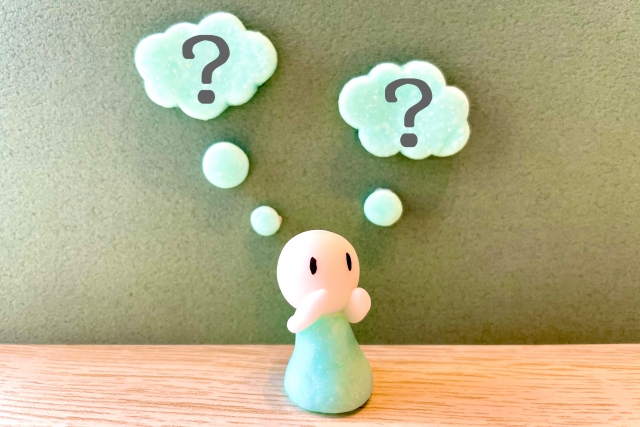
少子高齢化の進展に伴い、介護職の重要性が増していますが、介護現場には特有のリスクも存在します。腰痛や感染症といった健康被害に加え、利用者からの暴力や精神的なストレスも、介護職員の負担として知られています。こうしたリスクに直面した際、労災として認定されるかどうかが重要な問題となります。
特に介護職では、日常的な体への負担が大きく、腰痛を引き起こす無理な姿勢や動作が頻繁に求められます。また、感染リスクの高い職場環境や、利用者からの暴力による負傷も労災として認定される可能性があります。今回は、介護の現場で発生し得る労災について、その具体例や認定基準を詳しく見ていきます。
2. 社会福祉施設における労災発生状況

まず、介護職の労災がどの程度発生しているのかを知るために、社会福祉施設での労災発生状況を確認しましょう。厚生労働省のデータによれば、令和2年における社会福祉施設での労災による死傷者数(休業4日以上)は13,267人に達しました。これは、前年から32.1%、平成29年から51.8%という大幅な増加を示しており、介護職員の労働環境の厳しさを物語っています。
労災の内容としては、介護施設の種類によって異なる傾向があります。訪問系や通所系の施設では、最も多い労災が「転倒」であり、次に「動作の反動・無理な動作」が続いています。一方、短期入所系や居住系、施設系の介護施設では、「動作の反動・無理な動作」による事故が最も多く、次に「転倒」が多いという結果です。
これらの労災は、利用者の体を支えたり移動を補助したりする際の無理な姿勢や急な動作、または日常的な介護作業の中での不意の転倒が原因となっています。労災発生の増加は、介護職員の心身にかかる負担がますます大きくなっている現状を反映しています。
3. 介護現場での腰痛やケガは労災になる?

それでは、具体的に介護職員が腰痛や新型コロナウイルスに感染した場合、それらが労災として認定されるかどうかについて詳しく見ていきましょう。
3-1. 腰痛の労災認定
介護職の労災の中で最も一般的なのが腰痛です。介護現場では、利用者の体を抱えたり、ベッドから車いすに移乗させる際に、腰に負担がかかりやすい動作が頻繁に求められます。このような状況下で発症する腰痛は、労災として認定される可能性があります。
腰痛の労災認定には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
• 災害性の原因による腰痛:仕事中の突発的な出来事(例えば、急に利用者が重心を崩した際に体を支えるなど)が原因で、腰に強い力が加わり、腰痛を引き起こした場合。この場合、急激な動作や予期せぬ力が加わったことが重要な要件となります。
• 災害性の原因によらない腰痛:突発的な出来事がない場合でも、日常的に重い物を扱う仕事(例えば、利用者を毎日何度も移乗させるなど)を続けた結果、腰に慢性的な負担がかかり、腰痛を発症した場合。このように、作業内容や負荷のかかり方から、仕事が原因で腰痛が発症したことが明らかであれば労災として認定されます。
ぎっくり腰について
一方、ぎっくり腰は一般的に労災認定の対象になりにくいです。ぎっくり腰は、日常的な動作(例えば、腰をひねる、前かがみになるなど)で発症することが多く、労災認定の基準となる「突発的な災害」や「過度な負担」に該当しないことが多いからです。ただし、特定の急激な動作が原因で発症した場合には、労災として認められる可能性もあるため、個別の状況をしっかりと確認する必要があります。
3-2. 利用者からの暴力によるケガや精神的ストレス
介護職員が利用者からの暴力や暴言によってケガを負うケースも少なくありません。この場合、業務中に発生した出来事であり、業務起因性および業務遂行性が認められるため、労災として申請することができます。
• 業務起因性:介護業務中に利用者から暴力を受けたことが原因で発生したケガであること。
• 業務遂行性:業務中、つまり事業者の管理下で起こったケガや精神的な障害であること。
この2つの要件が満たされれば、暴力によるケガは労災として認定される可能性が高いです。また、利用者からの暴言により精神障害を発症した場合も、労災として認定される可能性がありますが、精神障害の場合は客観的証拠が必要であり、認定のハードルは高くなります。
4. 新型コロナウイルス感染は労災になる?

介護職員が新型コロナウイルスに感染した場合、その感染が労災として認定されるかどうかは、感染経路と業務との関連性によります。
• 感染経路が業務によるものが明らかである場合:例えば、施設内での利用者や同僚との接触により明確に感染したと判断される場合は、労災として認定されます。
• 感染経路が不明でも感染リスクの高い業務に従事していた場合:介護職のように、日常的に人と密接に接する業務に従事していた場合、感染経路が特定できなくても労災認定されることがあります。
つまり、介護職員が施設内で感染した場合、業務外での感染が明らかでない限り、労災保険の補償対象となるケースが多いです。また、新型コロナウイルスの後遺症が長期間続いた場合でも、療養等が必要と判断されれば労災保険の対象となります。
5. 介護現場での労災事例

ここでは、実際に介護現場で発生した労災事例を2つご紹介します。
事例①:トイレ介助中の腰痛発症
デイサービスの職員であるAさんは、トイレ介助のために利用者を抱きかかえて移動させている最中に、突然強い腰痛を発症しました。この場合、利用者を支える際に予期せぬ力が腰に加わったことが明らかであり、「災害性の原因による腰痛」として労災認定される可能性が高いです。
事例②:コロナ感染による労災認定
介護施設で働くBさんは、日常的に新型コロナウイルス感染が疑われる利用者に接していました。Bさん自身もその後、新型コロナウイルスに感染が確認されましたが、感染経路を特定することはできませんでした。それでも、Bさんが業務中に感染リスクの高い状況に置かれていたことが考慮され、業務による感染である可能性が高いと判断され、労災として認定されました。
6. 労災認定後に受けられる給付金とは?

労災が認定されると、労災保険から給付を受けることができます。給付には複数の種類があり、介護職員がどのような状態かによって受け取れるものが異なります。ここでは、代表的な給付金について説明します。
6-1. 療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労災によるケガや病気の治療費が補償されるものです。具体的には、以下のような項目が補償の対象となります。
• 医療費:診察や治療にかかる費用。
• 薬剤費:処方された薬の費用。
• 手術費用:ケガや病気の手術にかかる費用。
• 入院費用:入院に伴う費用、病室代、看護代など。
この給付は、ケガや病気が治るまで継続的に支給されるため、療養中の経済的な不安を軽減することができます。また、療養費は現物給付が基本となっており、労災指定病院での診療であれば、窓口での支払いなしで治療が受けられます。
6-2. 休業(補償)給付
休業(補償)給付は、労災によるケガや病気で働けなくなった場合に支給されるものです。支給される条件として、以下の3つを満たす必要があります。
• 労災による傷病を負っていること:労災認定されたケガや病気であることが前提です。
• 労働ができない状態であること:医師の診断によって、労働不能とされることが必要です。
• 賃金を受けていないこと:ケガや病気のために働けず、賃金を受け取っていない期間が対象となります。
この給付金は、休業4日目から支給されます。休業1日目から3日目までは、待機期間として給付は発生しませんが、4日目以降、賃金の60%相当額が支給されることになります。さらに、治療が長期化し休業が続く場合でも、要件を満たしている限り支給が続きます。
6-3. 傷病(補償)年金
もしも労災によるケガや病気が長期間にわたって治らず、休業補償だけでは補いきれない場合には、傷病(補償)年金を受け取ることができます。この年金は、治療開始後1年6か月経過しても症状が固定せず、かつ障害が残る場合に支給されます。
傷病(補償)年金は、労災認定された傷病の等級に応じて支給額が異なります。等級が高いほど、年金の支給額も増えます。また、支給は治療が続く間は継続されるため、長期的な療養を必要とする介護職員にとって、経済的な安心材料となります。
7. 労災の申請手続き:どうすればいい?

労災の認定を受けるためには、労災申請を行う必要があります。ここでは、労災申請の流れについて解説します。
7-1. 申請の流れ
1. 労災の発生報告
労災が発生したら、まず職場の担当者に報告しましょう。事業者側は労災が発生したことを労働基準監督署に報告する義務があります。
2. 必要書類の準備
労災申請には、労災給付請求書や医師の診断書などが必要です。これらの書類は労働基準監督署の窓口やインターネットで入手できます。
3. 申請書類の提出
必要な書類をすべて揃えたら、労働基準監督署に提出します。提出後、審査が行われ、労災として認定されるかどうかが決定されます。
4. 給付の開始
労災が認定されると、該当する給付金の支払いが開始されます。療養(補償)給付や休業(補償)給付は申請から比較的早い段階で支給されることが多いです。
7-2. 会社が労災申請を拒否したら?
残念ながら、一部の事業所では「労災申請をしないでほしい」と言われるケースがあるようです。しかし、労災は労働者の権利であり、事業者が申請を妨害することは違法です。もし労災申請を拒否された場合は、労働基準監督署に直接相談するか、弁護士に相談することが推奨されます。
8. まとめ:介護職員が労災に備えるために

介護職は、日々多くのリスクを伴う職業です。腰痛や新型コロナウイルス感染、利用者からの暴力など、さまざまな労災のリスクがあります。こうしたリスクに備えるためには、労災の認定基準や補償内容を理解し、万が一の際に適切な対応が取れるようにしておくことが重要です。
労災が認定された場合、療養や休業の補償を受けられるため、経済的な不安を軽減することができます。労災に関する疑問や不安がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談し、しっかりとサポートを受けることが大切です。
介護現場での労災リスクを最小限に抑えるためにも、事業者と労働者が協力して安全な環境を作り上げていきましょう。







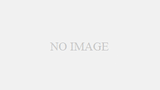
コメント