
皆さんこんにちは!ロマです!
こんにちは!ロマ子です!今日は何について勉強していくのかな?
今日は『高齢者を狙う特殊詐欺』についてです!
とても気になりますね!考えるいい機会ですね!
では皆さんで一緒に勉強しましょう!
特殊詐欺とは?
特殊詐欺とは、特定のターゲットに対して巧妙な手口を使って金銭をだまし取る犯罪です。特に高齢者を狙った詐欺が増加しており、その手口はますます多様化しています。最もよく見られる特殊詐欺は、「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「預貯金詐欺」などで、犯人は電話や訪問を通じて高齢者を信用させ、金銭を要求します。
高齢者を狙う特殊詐欺の実態
警察庁が発表した「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」によると、令和4年(2022年)の特殊詐欺の認知件数は17,570件、被害額は370.8億円にのぼります。そのうち、65歳以上の高齢者が被害にあった件数は15,114件で、総認知件数の86.6%を占めています。特に高齢女性の被害が目立ち、女性被害者の認知件数は11,559件となっています。
高齢者が詐欺に遭う原因としては、詐欺グループが巧妙に高齢者の不安を利用し、精神的な隙間をつけ込むことが挙げられます。詐欺師は「家族のため」や「急を要する事情」を持ち出して信頼を築き、金銭をだまし取ります。これにより、高齢者は「自分のためにやっている」と信じ、被害にあうことが多いのです。
高齢者特殊詐欺の事例
高齢者を狙った特殊詐欺の実際のケースを見てみましょう。
-
長野県の還付金詐欺
2023年9月、長野県に住む70代女性が役場職員を名乗る男から「介護保険料の払い戻し金がある」と電話を受け、ATMを操作して407万円を振り込んでしまいました。後日、この電話が詐欺であったことに気付きましたが、すでにお金は振り込まれており、深刻な被害を受けてしまいました。 -
北海道の投資詐欺
北海道では、SNSで知り合った投資家を名乗る人物から「株式投資で大きな儲けが出る」と勧められ、70代男性が信じて1,200万円を振り込んでしまう事件が発生しています。後にその投資が詐欺であったことが判明し、大きな損失を被ることとなりました。
これらの事例からもわかるように、詐欺の手口は非常に巧妙で、高齢者が信用しやすい状況に乗じて金銭をだまし取ります。
高齢者が特殊詐欺に遭いやすい理由
高齢者が特殊詐欺に遭いやすい背景には、いくつかの要因があります。
1. 高齢者が抱える3つの不安
高齢者が詐欺に遭いやすい理由の一つは、「お金」「健康」「孤独」という3つの不安にあります。高齢者は、生活の中でこれらの不安を常に抱えているため、詐欺師はこれらの不安を巧みに利用して近づいてきます。例えば、介護や医療費がかかりすぎる不安を感じている場合、還付金や税金の払い戻しという名目で詐欺に遭うことがあります。
2. 家にいる時間が長い
退職後の高齢者や一人暮らしの高齢者は、日中家にいることが多く、電話に出やすい時間帯が増えます。これにより、詐欺師からの電話に出てしまうリスクが高くなるのです。また、高齢者は聴力が低下していることも多く、電話の相手が家族の声を装っていても聞き分けにくく、詐欺に気づくのが遅れる場合があります。
3. デジタルリテラシーの低さ
インターネットやSNSに不慣れな高齢者は、詐欺の手口を知る機会が少なく、詐欺師の巧妙な手口に気づきにくい状況にあります。最新の詐欺手口は、インターネットやSNSを通じて広まることが多いため、高齢者が情報を取り逃す可能性が高くなります。
4. 自分だけは大丈夫と思ってしまう
多くの高齢者は、テレビや新聞で詐欺のニュースを見ても「自分だけは大丈夫」と思い込んでしまいます。しかし、実際には、被害に遭っている人の多くが自分は詐欺に遭わないと思っていた人々です。過信が招くリスクを理解し、常に警戒心を持つことが重要です。
高齢者特殊詐欺の対策
高齢者が特殊詐欺に遭わないための対策として、家族や高齢者本人が実践すべき方法を紹介します。
1. 電話対応の対策
高齢者が電話で詐欺に遭うことが多いため、以下の対策を取るとよいでしょう。
-
留守番電話を設定
在宅時でも留守番電話を設定し、不審な電話を受け取らないようにします。留守番電話のメッセージに「詐欺に注意!」という文言を入れると、さらに効果的です。 -
ナンバーディスプレイの導入
ナンバーディスプレイサービスを利用すると、電話番号が表示されるので、知らない番号からの電話には出なくて済むため、詐欺に遭うリスクを減らせます。 -
家族専用の合言葉を決める
家族間でしか知らない合言葉を決めておき、万が一、家族を名乗る人物から電話がかかってきても、合言葉で真偽を確認できるようにします。 -
詐欺の常套句を掲示する
家の電話付近に「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」の常套句を掲示しておくと、詐欺師からの電話に気づきやすくなります。
2. 定期的な情報収集
高齢者本人がテレビや新聞でニュースを確認することはもちろん、家族がインターネットで情報を収集し、簡単に伝えることが大切です。また、自治体の広報誌や警察署のチラシなどにも詐欺に関する情報が載っていることがありますので、チェックしておくとよいでしょう。
3. 家族との連携
「携帯番号が変わった」と連絡があった際には、いったん切って、必ず元の番号にかけ直して確認する習慣をつけましょう。また、お金に関する電話がかかってきた場合には、すぐに対応せず、必ず家族や信頼できる人に相談することを徹底しましょう。
4. 金銭の取り扱いに関する注意
- キャッシュカードやクレジットカードを渡さない
警察官や自治体職員がキャッシュカードを要求することはありません。もし「カードを見せてほしい」と言われた場合は、即座に疑いを持ち、警察や市区町村役場に確認しましょう。
被害に遭った場合の対応
もし詐欺に遭ってしまったと気づいた場合、迅速に対応することが大切です。以下の相談窓口を利用しましょう。
- 警察の電話相談窓口: #9110
- 消費者ホットライン: 188(いやや!)
- 消費生活センター
自己判断せず、迅速に相談し、警察や消費生活センターに対応をお願いすることが重要です。
まとめ
高齢者を狙った特殊詐欺は年々手口が巧妙化しており、その被害は広がっています。しかし、家族や高齢者本人が対策をしっかり講じていれば、被害を防ぐことが可能です。「自分だけは大丈夫」と過信せず、常に最新の情報を収集し、詐欺の手口を知っておくことが大切です。万が一、詐欺に遭った場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談し、適切な対応を取るようにしましょう。







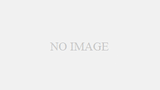
コメント